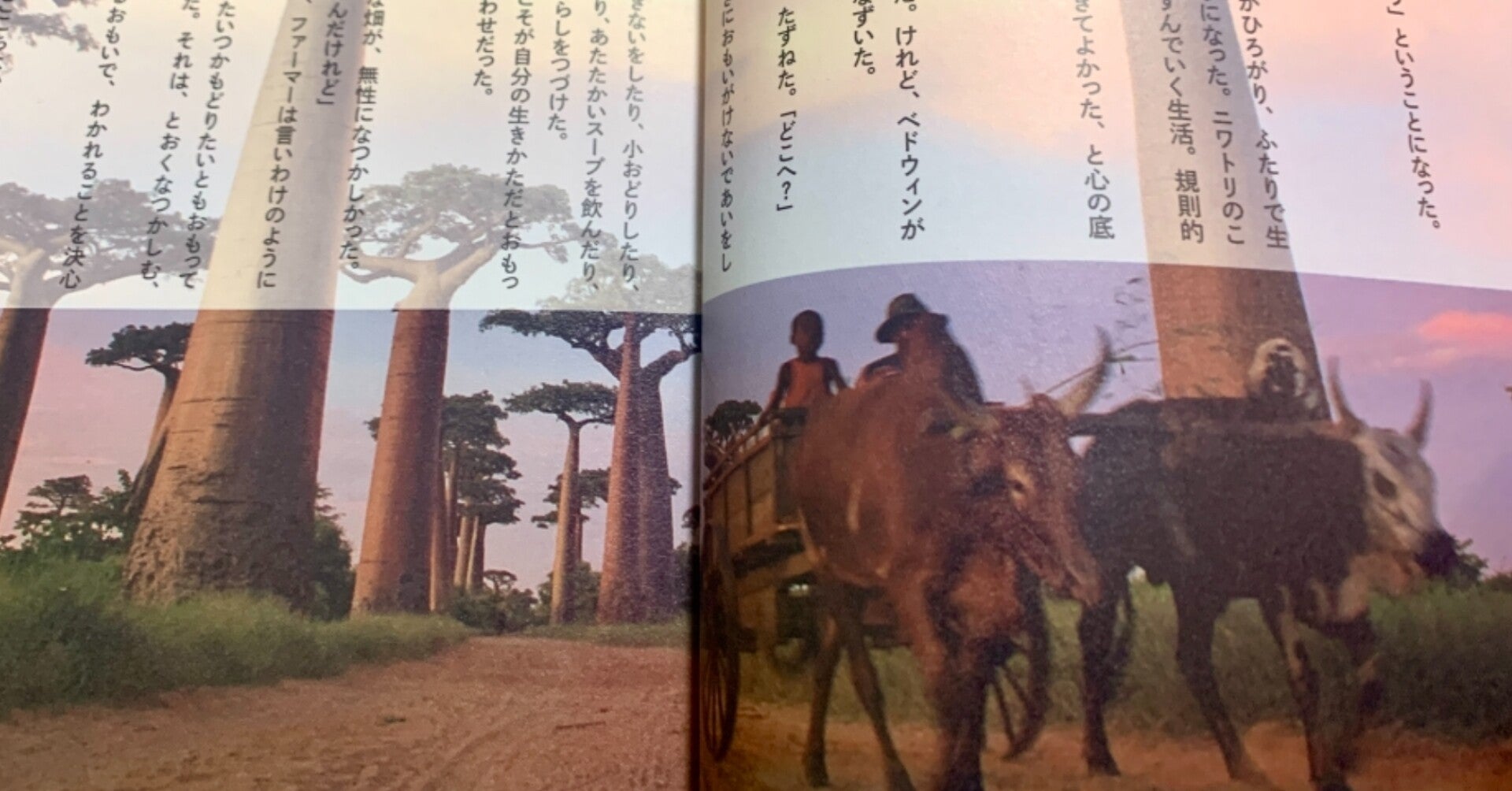その1. 売り込む。
2009年から2011年にかけて東南アジアから南米まで西廻りで世界旅行をし、そのエッセイを2014年に出版した。
1年半の旅から帰って来た時、本を出すことだけは決めていた。ただどうやって出せばいいのかはまったくわかっていなかった。なにせコネもなにもない。ただ出すと決めていただけ。なので可能性と方法を模索することにした。
考えた末、思いついた方法を実行することにした。
といってもその方法は至ってシンプル。思いつく人は他にもいると思う。
Wikipedia出版社網羅作戦。
Wikipediaには「日本の出版社一覧」というページがある。そこからリンクを貼ってあるすべての出版社のページに飛び、紀行本を出したことのある出版社のリストを作った。その中から有力候補三十社を選んだ。
少なくともこの三十社はすべて当たるつもりだった。だめだったらその時はまた別の方法を考えよう、と。
素人が本を出す時にすることとしては、主に2つあると思う。1つは企画を売り込むこと。2つめは原稿を送ること。私は後者だった。原稿はすでにあったので、送る前に電話をし、ハナからけんもほろろな感じでなければ、A4の分厚い紙束を候補の出版社に送るという形を取った。正直にいえば、電話せずにいきなり送った会社もあったように記憶している。
原稿を書いたのは、旅の間だった。正確にいえば、旅の間に三分の二、残りを帰国後に。旅の間は自分に締め切りを設けるためブログを利用した。ただ誰に頼まれたわけでもない締め切りであるために効力は弱く、さらに旅中はなにかと忙しく途中放置、残りを旅の最後に立ち寄った国で書き、それでも終わらず、残りを日本で書いた。そのへんは本にも書いたのでここでは詳細は省く。
最後まで書き終えた時に原稿用紙に換算して1000枚以上あったので、校正もかねてほぼ半分に削った。それでも多すぎるだろうとは思ったけれど、そこからさらに削るのは話が実際に進んでからでいいと考えた。一冊の本になるように流れを考え、体裁を整えた。
企画を売り込むより、最初から現物を読んでもらうことしか頭になかった。けれど、長いのはわかっているので、読んでもらうためにどうしたらいいかを考えた。そこでまずA4用紙数枚で要約を書いた。加えて、推したい章には付箋をしてメモをつけた。出したいのはあくまで文章主体の本であったけれど、写真も目を引きそうなものを選んで添付した。
さらに、こっぱずかしい気持ちと、全力で抵抗する内側をなだめながら、自分なりの売り文句も添えた。主に、アラフォー女ひとり旅ということと、旅するために離婚した点をプッシュした内容で。40前後であることは事実でもアラフォーと言う言葉自体はあまり好きではなかったし、離婚を売りにすることも身を売るようで気が進まなかったけれど、旅が発端となって離婚に至ったのは事実であったし、なにより、
「なにものでもない人の本を出したいと思ってもらえるにはどうしたらいいかねえ」
できあがった原稿を読んで細かく感想を伝えてくれた幼馴染みの言葉もあった。そうだよね。自分でも感じていたことを指摘され、この期に及んで恥ずかしがっている場合ではない、と腹をくくった。
できあがった原稿を出版社に送る前に、人に読んでもらうことは決めていた。何人か候補がいたが、第一候補のひとりとこっそり決めていた文章に携わる仕事をしている友人は、それとなく本を出そうと思っていることを伝えた時にあまり肯定的な反応が返って来なかったために、やはりこっそりとひっこめた。
他にも、文章に携わる人ということで、お世話になった翻訳学校の人に送ってみたりもした。これは正直自分でもあかんかったと思う。お忙しいのに、本当に今考えてもいい迷惑だったのではと思う。それでもそんなことはおくびにも出さず、丁寧な応援のメッセージをくださった。
幼馴染とは、なにがあったというのでもなくお互いの結婚だったり離れて暮らしていたこともあって、長い間に縁遠くなっていた。けれど、旅を始めてから、ブログを通して関係が復活したような、復活というか、時々感想を伝えてくれたり、危ない地域を通り過ぎた時には声をかけてくれるなど、旅を見守ってくれている感じがあった。
本好きな彼女なら的確な意見を言ってくれるのではないか。そうはいっても当時小さい男の子二人のお母さんであり、労力のいることをお願いしているのはよくわかっていたので無理なら断ってもらって全然かまわないことも伝えたうえで頼んでみると、二つ返事で承諾してくれた。
そう長い期間をおかずに読み終わったという連絡が来て、彼女の住む県に向かい、おすすめのとんかつ定食を食べて彼女の家に向かった。居間に入ると、付箋だらけで赤がいっぱい入っている私の原稿と、A4用紙4枚にぎっしり書かれたメモがテーブルの上に置かれていた。付箋とメモをひとつひとつたどりながら、ここは冗長、ここはよくわからない、いらないんじゃないか、ここはよかったからプッシュしたらいいと思う、など丁寧に説明してくれた。終わる頃にだんなさんと少年ふたりが帰ってきた。
続きます。
とほ