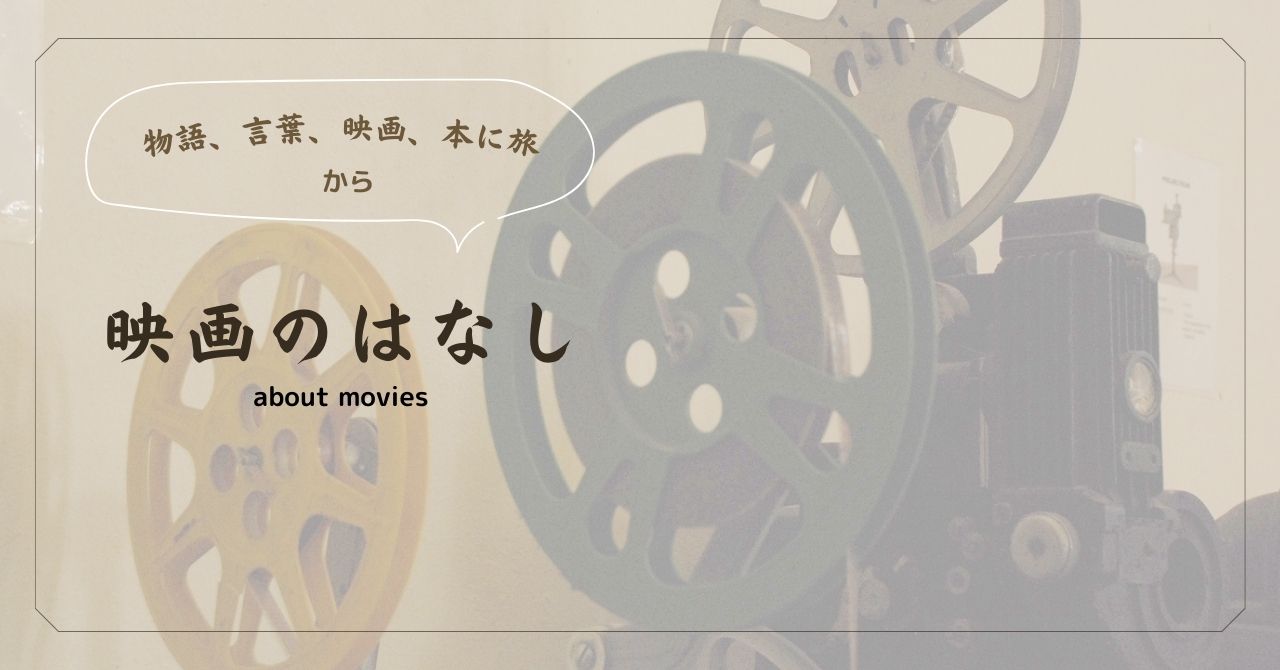”時が癒すといったって、もし時が病気だったら?”
ヴィム・ヴェンダース『ベルリン天使の詩』より
『天才と発達障害 』(講談社、岡 南著)という本で、人は視覚優位(ガウディ)型と聴覚優位(キャロル)型に分けられるというのを読んでから、例えばターセム・シン『落下の王国』で、映像美を褒めたたえる人と物語に持っていかれる人がいることに、非常に納得がいく気がしている。
『落下の王国』の場合、私は圧倒的に後者だ。
インド映画『パドマーワト』をみた時には、公開時に感想を読んでいて、サンジャイ・リーラ・バンサーリー監督の作品が好きな人は視覚優位の人が多そうだなと感じた。そもそも監督自体が視覚優位なのだろう。少なくとも私の中では5本観た時点でそう確定した。正直、ストーリーは単調と感じることが多い。時間も長めなので、最終的に胸を打つ映画であっても間延びして感じる(とくに初見時は)。でもこの監督の場合はむしろそこを「壮大だ」と感じさせるだけの映像美がある。装飾や時代背景で奥行きをもたせた映像美にインド映画の舞と音楽の躍動が加わることによって。パドマーワトの二度目に、ストーリーはあくまでそれらを見せるための軸という意識にシフトしたというかそうなってたというか、そういう態度で観たらまったく退屈しなかった。そうやって没入した先には物語的な昇華も待っていた。
ただ、私が胸を鷲掴みにされる監督かというとちがう。
本の話に戻すと、ガウディというのはもちろんサグラダ・ファミリアの建築者アントニオ・ガウディのことであり、キャロルというのは『不思議な国のアリス』のあのルイス・キャロルだ。タイトルが発達障害となっているけれど、もちろんそれにも触れているけれど、多くは、視覚優位型と聴覚優位型の人のものの見え方、捉え方についてページが割かれている。各人の発言や記述から、ふたりの見えていた世界が明確に異なっていたことが推測される。言うまでもなく、視覚優位なのがあのとてつもない空間芸術を組み立てたガウディで、聴覚優位なのが言葉で遊ぶ達人ルイス・キャロルだ。
そして、画一的にわけるのは好きじゃないんだけれども、映画観(み)は、視覚優位か聴覚優位かどちらが優位かによって、観るポイントに違いが如実にあらわれる気がしている。
映画観賞者の観点から
私はキャロル型なのを自覚している。ここからは、自分がそうであるという意識を持つ者のごたくだけど、映画にふれる時、聴覚優位の人はセリフや物語を重視しがちで、一方視覚優位の人は構図や配色に対するこだわりがすごいように思う。
聴覚優位な私には、多分視覚優位な人の見ているものがそこまで見えてない。視覚派の人の良い意味で重箱の隅をつつくような鋭く細かい点が、指摘されるまで私にはまるで見えていなかった、というようなとこはわりとよくある。そのへんの描写のうまさにはある程度技術/ハード面への精通も必要なようにも思うけど、でも専門用語を使わずとも、膝を打ちたくなるような指摘をする人はいくらでもいる。そして、映画みとして、正直、その微細な指摘やセンスに脱帽し、羨ましく思うこともある。
とはいえ、じゃ、おまえは映画観ずに小説でも読んでろ、と言われるなら、それも違うんじゃない?と思うわけだけど。そもそも言われてない。言われてないけど、「映画と文学はちがう。映画に文学を求めるな」みたいな意見が目の前を通り過ぎていった記憶がよみがえったのでつい。
私は、本という平面上に著者の筆力と読み手の想像力だけで立ち上がる世界も愛しているし、脚本、編集、演技の組み合わせで化学変化を起こす立体魔術も愛している。
私自身は、映画では、どうしても物語重視だし、言葉、台詞にひかれてしまうことが多い。映像にのせられる言葉・台詞に印象的なものが多いほど、物語が自分のエッジにびんびんくればくるほど、その映画が自分にとって特別になる傾向がある。
具体的にいえば、たとえば、ああこれ書くとものすっごいシネフィルの人に怒られそうだけど、正直、タルコフスキーは私はぴんとこない。冗長に感じてしまうし、「そんな静物画みたいな構図、舞台でやれや‥‥‥」などと珍暴言を心の中で吐いてしまったりもする(あうう)。
とはいえ、タルコフスキーの中では『惑星ソラリス』は好きだ。でも原作者S・レムと袂をわかったというのはなんかわからなくもない。なぜなら、映画は映画として楽しんだけれど、原作と映画は別物と普段わけてはいるけれど、実のところ持っていかれたのは圧倒的に原作の文脈の方だからだ。
反面、ヴィム・ヴェンダース『ベルリン天使の詩』のような、言葉に身を委ねて心地よい映画が大好きだ。そこには宝物のような言葉にあふれていて、初見時はいちいちビデオを止めては書き留めるなどしており、まずはちゃんとみよう?自分?と言い聞かせないといけないほどだった。昨年、劇場でリバイバル上映があった時には、時を経て、まったく変わってない自分を自覚した。ただひたすらここちよかった。ここまで言葉をつむげるということは、ヴィムヴェンダースもまたそうなのかな、聴覚優位なのかな、なんて思いたくなる。
観客/受け手にも視覚優位と聴覚優位がいるように、作り手/送り手にも当然、両方いる。どっちが優勢かは作品に如実にあらわれるなあ、と思う。映画を撮るには多分有利なのは視覚優位型なんだろう。一方、脚本家は聴覚側の感性が欠けていると厳しそうな気はする。
とはいえ、映画のよさは、いくら言葉や物語が鷲掴み要素でも、やはり映像あってこそ。映像なくしては成り立たない。台詞がしみいる、言葉が大切に扱われている映画が好きだけど、映画の良いところは、それに寄り添う映像がある点だ。
最初に絶賛され、のちにけなされまくった『アメリカンビューティ』も、同じ理由で今でも好きだ。賞を取ったとか、その後の脚本家に対する人々の上げ下げとか揶揄とかは関係ない。あの有名なフレーズを始めとする数々の印象的な台詞も、閑静な住宅街に舞うビニール袋も、いまだに等しく美しく私の中にある。
なんだかとりとめもなくなってきたけど、
1つの対象物に対する感想や意見や見え方を人と話す時に、同じものをみているのにまったく違うものがでてくることがおきる。その要因は他にもあるだろうけど、この聴覚優位と視覚優位というのを知った時に、すごく腑に落ちた気がした。ここがすべての答えとも思わないけど、なーるーほーどーなーとは思った。
視覚派のみているものと聴覚派のみて(感じて)いるもののちがい、これはあくまで性質なので、感情論としての「わかりあえない」ではなく、ただ単に根本的にちがっているのだ。ガウディにみえているものとキャロルにみえているものがちがうように。
どちらがまちがいとかじゃなく、ただ本当に、みえているものがちがう、ということはあるのだ。
とほ